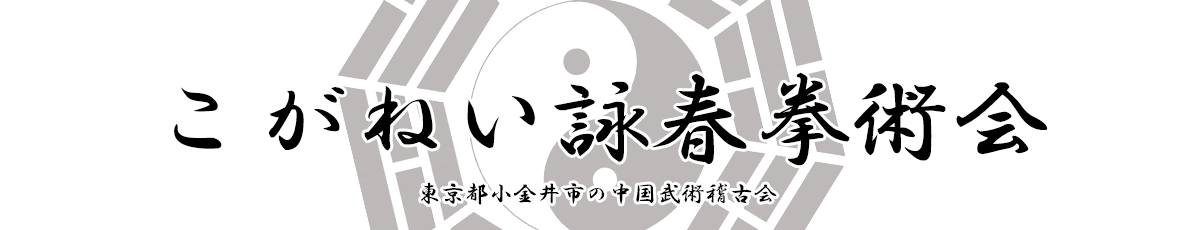上段を大きな力で押し込まれた場合の対処法
手首と指先の感覚・コントロール
詠春拳の型『小念頭』の第4段目の途中にある「小さい前ならえ」を作る状態のポイントです。 ラーンサウから拂手をし、またラーンサウに戻ってきてから大きな十字を作って腹の前まで落とし前腕2本をほぼ平行に揃えます。 このときの手首と指の緊張がないのは間違いで、見ただけで抜けが生じているのかがよくわかります。 抜けが生じているときは、上から少し力を加えてやると手が落ちてしまうし、下から交叉しして持ち上げてやると「ふわっ」と簡単に手先が浮いてきます。
このような場合は、私は相手の手首から手の甲を擦り、薬指または中指に抜ける意識のルートを示してやります。 すると不思議なもので、指先に気が入り、手先が軽くなりません。この状態を作って、 上からと下からの交叉で検査をしてみるとかっちりした腕の構造ができていることが納得してもらえます。

上の伏手を大きな力で押し込まれたらどうするか?
詠春拳の練習の終わりくらいに練習生から質問がありました。 「自分の上の伏手に対して、相手が膀手なり拂手で強い圧力をかけてきて押し込まれる場合があるのですがどう対処したらよいですか?」という質問でした。 これはよくあることであり、いい質問ですね。
まず大事なのは相手の真っすぐ向かってくる力を堪えないこと。接点圧力が増幅するのであれば、その分、足を使って移動し角度を変えます。 さらに相手が前進し圧力を加えてくる動きに合わせて少し加算的に力を加えてやり「引進落空」の状態を作ってやります。 このとき、力を加える方向は下方向でよく、相手の上の膀手や拂手を落とす形になります。 ただ、このときの感覚が詠春拳の上級者と初学者とは違うようで、相手の崩れ方に違いがあらわれます。 上手くいかない結果としては、相手は下方向の力に対して肩の力を抜いて、腕を下げるだけで終わることがあります。 腕の脱力だけで対処できてしまい、体軸に影響が出ないのです。当然、膝から崩れるという現象が起きません。
それに対して、タイミングや力のかける方向がよいと相手はつんのめるように崩れます。 体軸に影響が出るのです。この感覚は実際にやって体験してみないとわからないくらい微細な違いです。

浮きをかける
詠春拳の練習後、憩いをとって残っていた練習生に沈み込み(下方向)と、パンチの打ち出し(水平方向)の共通した身体の使い方を伝授しました。 伝授というと大袈裟な表現ですが、常日頃からいっている浮きの感覚をより丁寧に解説しました。 縦に構えた自分の前腕を相手が両手でガッチリ握って押さえた場合や、相手が両手で自分の拳を押さえた場合、 体重をかけようとグイグイ押したり、逆に後ろに引っ張ったりしても相手は強い力で反発してきます。 このとき、身体を前や後ろに傾けるのではなく、足裏を浮かすように身体全体を浮かせる感覚があると、 身体がひとつにまとまり身体全体の力を相手の骨格に送り込むことができますので、うまくいけば相手の膝まで崩すことが可能です。 とはいえ、書くのは簡単ですが、実際にやるのは難しいので、何度も挑戦し失敗しながら感覚を掴んでいくほか方法はありません。