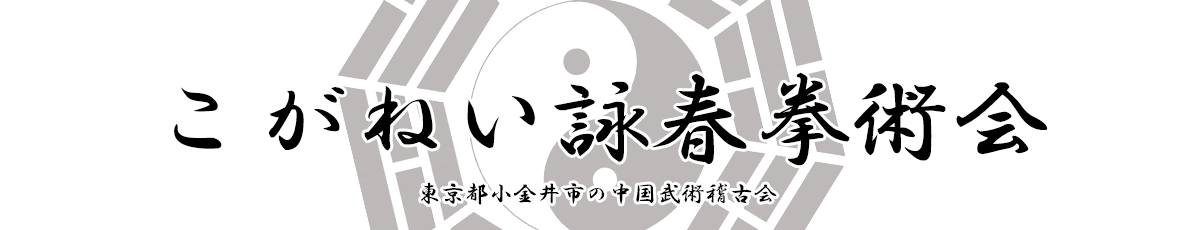上からのしかかるような押さえ込みの対処法
肘を浮かし手先を下げるような押さえ込みの対処
自分の攤手を相手が肘を浮かせ、手首を下に静めるように押さえ込んできた場合はどう対応するかといういい質問がありました。 手先がぐっと下に下がるような伏手の受け方をするのは詠春拳の修行を開始した初心者にありがちな動きなのですが、 初心者といえども腕力の強い人が押さえ込むと、力がぶつかってしまい、詠春拳の技術がそこそこできる人でもどうにもいかなくなります。
これに対するひとつの方法としては、相手の手先の重さを自分の肘の方に持ってくることです。 これは自分の肘を下に落とし、自分の手先はアッパーをするような感じで持ち上げます。 これは合気上げの原理に近いものでもあります。 そうすると、相手の押さえ込もうとする腕を持ち上げることができなくとも、相手の重心を浮かすことはできるはずです。 相手の重心が浮いて、押さえる力が弱くなったらそのまま相手の腕を突破し、もしそれでも意地になって腕力で押さえ込もうとするならば、 腕はそのままアッパーのような腕の形をキープした状態で転身して横方向に振れば、相手は崩れるでしょう。 これに耐えられる人はほとんどいないと思います。
もちろん、これは腕力で下方向に押さえるという間違った条件があるからできることで、 下段の内門から侵攻する力は、窒手などの前後方向の動きで適切に処理されれば崩されることはありません。

掌から手首をガッチリ握られた場合
指のかかり方、接触部の骨格を感じ取って、相手の骨格に力が通るようにします。 相手の指がガッチリ噛んでいる場合は、相手の指先と親指の付け根あたりの2か所に同時に力を送り、 相手の前腕骨に力を通し、相手の抵抗反応を使って崩すことになります。 梃子の原理が働きますので、ガッチリ握られて相手の指が噛んでいるほうが崩しやすいでしょう。
逆に相手の指があまり噛んでこないようでも相手の親指の付け根あたりの骨を感じ取って力を送り込むと、 相手が抵抗するならば崩す力を通すことができます。相手の握りが弱いので梃子の原理は使いにくいですが、 手が離れれば即座に顔面に打撃を入れるぞという力と意念が伝われば相手は必死になって押さえようとします。 接触部位の接点圧力が高まれば、指が噛んでなくても相手の骨格に力を送り込むことは可能なのです。

拂手(ファークサウ)の首の後ろ側の感覚について
詠春拳の型『小念頭』における拂手の力感覚を確認するのに、お互いに向き合って拂手の手首あたりを接触させて、 片方は開く、片方が堪えるようにして確認をします。このとき、力が出にくい人の特徴として、 首の後ろ側の意識が抜けてしまっている感じがします。首の後ろといっても、喉の後ろではなく鎖骨のつなぎ目の背中側というあたりです。 ここら辺をまっすぐにする意識をもつと肩回りの構造が整い拂手の力が出しやすくなるでしょう。