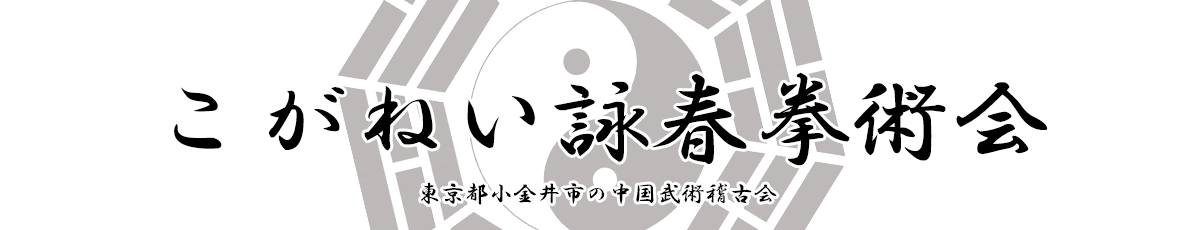上の膀手+下の攤手で入っていく詠春拳独特の技法
上の膀手+下の攤手で入っていく
詠春拳においてはよくあるパターンなのですが、自分が下の攤手+上の膀手の状態のとき、 両腕がインサイドの交叉の状態から角度を取りながら入っていく技法について説明しました。 両腕がインサイドを取れているときは基本的には有利なのですが、相手も警戒してガッチリ外から押さえてきますので、 ある程度技量がないと相手を崩すことができません。

多くの失敗例としては、角度が取れたなと思って前に進行することで相手を押してしまう場合があります。 相手に押す力をかければ相手は正中線を閉じながら下がります。下がられるとより深く入っていくことはできません。 それで今度は前への進行を自重して、しっかり転身の力を与えようと回転角を大きくすると、今度は相手を振りすぎて相手に腕を離されて、 すっぽ抜かれた状態で一人で回転することになります。
相手が自分の攤手の進行を押さえていないとまずいと感じる角度があり、 その角度をより外に無駄に振ろうとすれば当然抜かれます。 自然に入っていけるルートがあるのでそれを探るようにしてもらいたいです。
盤手のときの軸の話
盤手のときの軸感覚についてよい質問がありました。身体を前に傾けないで前に力を出すにはどうしたらよいかということでした。 例えば、長竿のような長い棒は真っすぐに立てても前方向の力を生みません。腕で押せば倒れてしまいます。 しかし、人間は、頭脳によるバランスの制御ができますので、倒れようとする際に、 真っすぐを保つために体幹の筋肉をコントロールして真っすぐをキープすることができます。
真っすぐに体軸をコントロールできれば、物理的には垂直抗力を最大に得ることができ、 それにより地面との摩擦力を最大にすることができます。とはいえ、地面との摩擦力を最大にしようと、 地面を足裏でこするような感覚は間違っているのでやらないで欲しいです。
体軸のコントロールさえうまくいけば、自然と地面からの力を得ることができるので、足裏を意識する必要はないかと思います。 詠春拳では体軸のコントロールに重きを置き、集中すべきだと考えます。
標手で転身力を活かして相手を崩す
練習の最後の30分ほど、練習生の多くが標手による転身の稽古に時間を使いました。 相対交叉(相手が右手の場合、右手で自分の左手首あたりを掴む)で腕をガッチリ押さえられたとき、 腕の下を通すように標手が抜けるかという課題です。転身をしようとしても、どうしても力がぶつかり、 ひっかかってしまうという問題が生じます。

これに関しては以前は転身力と腕の噛み合わせという説明をしていたと思いますが、今は、 接点のフィット感を大切にあまり相手にグイグイとした強い力をかけることなく優しい力で接点を連れて行くことが大切と説くようになりました。 そのほうが楽に相手を崩すことができると最近は考えております。 詠春拳の技術が向上すると、無駄な力が必要なくなるという面白さに気が付けます。